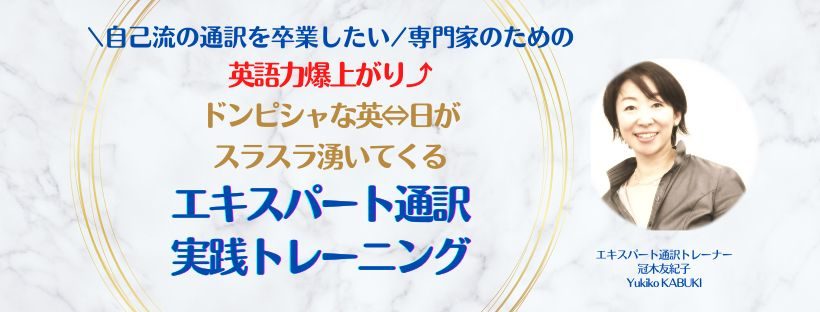大坂なおみ選手、I’m sorry it had to end like this.の訳は?
「大坂なおみ選手のインタビュー記事読んでたんだけど、翻訳に違和感があって。通訳者としてどう思う?」
30年来の友人からメッセージが来ました。日本語と英語両方チェックしてたのですね。さすが。
なんでも、I’m sorry it had to end like this.の出だしが「ごめんなさい。」になっていたとか。
あら、朝日新聞もそう。写真をクリックしてご覧ください。

あちゃー。
「ごめんなさい、勝ってしまって。」としている訳まであるとか。大坂選手、そんな嫌味を言う人柄とは思えません。
I’m sorry をひとかたまりで「ごめんなさい」と置き換えてはいけません。そんな訳には、大坂選手に倣ってI’m sorry it had to be translated like this.といいたいところ。私、ごめんなさいなんて言ってませんよ。
ものごとは「細かく割って見る」のが大切。カタマリはだめです。球が止まって見える一流選手は時間を細かく割っているといいます。言葉でもその感覚がないと不自由、誤訳のもとです。
sorryはsore痛み+y(形容詞化する語尾)。
喉が痛いのをsore throatと言う、あのsoreです。
ちなみにsoreの語源は古英語のsarig(ほんとはaの上にバー)。
ですから、I’m sorryはそもそも「私は心痛めています。」という意味です。そのあとに心痛める原因、状況が続きます。
たとえば…
「I am sorry a bright student like you have handed in something like this. 残念だね、君のように頭脳明晰な生徒が提出したのがこんなものだとは。」
「We are sorry the typhoon have totally damaged our crop.遺憾なことに、あの台風のせいで作物がみんなやられてしまった。」
I am sorry.が「ごめんなさい」になるのは、後半で言うはずの自分がやらかした失態を省略した場合です。
でも大坂選手は失態をやらかしたわけでも、後半を省略したわけでもありません。
I’m sorry it had to end like this.は「残念です、こんな終わり方になって。」といったところでしょう。
後半の主語をitとしてセリーナも自分も出さず、had to を使っています。誰も責めずに、最少限の語数で最大限の思いを表しています。大坂選手、口数の少なさも魅力です。
「なんだか残念だわ、こんな風に終わることになっちゃうなんて。」でも間違いではないのですが、なんだか同じなおみでも渡辺直美ちゃんぽいです。
「このような終わり方を迎えることとなり、心を痛めています。」となると天皇陛下です。
ひとりひとり、違うのです。
だから通訳者は徹底的に聴きます。翻訳も同じことです。よく聴いてから翻訳すれば、言語を超えても本人の息遣い、声が聞こえてくるものです。
そんなことできる?できます。やっています。そこまでやらないならAIにすべて任せた方がお客様のためです。