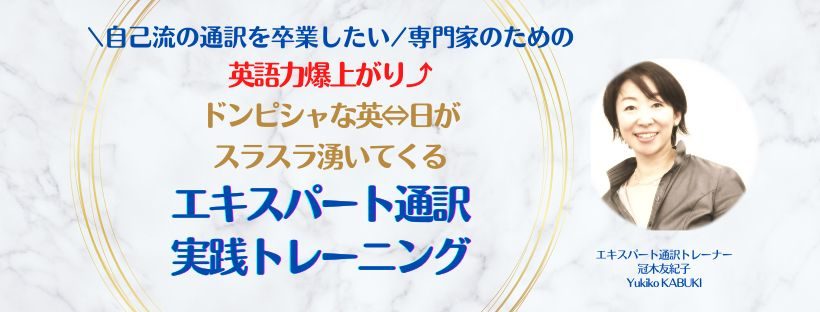横浜で明治の花嫁が書いた英詩
これまで2回にわたり、幕末、明治の横浜ではまさに諸国(日本国内、海外両方)のひとたちが入りまじっていたこと、ことばはナショナルなものではなく、目の前で話している「ひと」と結びついていたことをご紹介しました。ナショナルなきまりがなければ、どんどんまじりあっていくのもうなづけます。
でも、ちょっと事情の違う空間もありました。キリスト教の宣教師たちが開いた女学校です。こうした学校ではアメリカから教科書を取り寄せ、アメリカの学校のような教育がなされていました。ヘボン医師の施療所を借りて女子に授業を行っていたメアリ・エディ・キダーは本国宛ての手紙にこう書いています。

「…現在女性と12名です。そのうち7名は14歳から17歳まで、残りの5人は8歳から10才ですが、とても小柄なので、アメリカの5,6歳の子供のようにみえます。
少女たちはみな利発で、理解が早く、アルファベットの大文字、小文字を覚えるのに三朝以上かかった子はなく、1人は第1日目に全部覚えてしまいました。」(榎本義子訳「キダーの手紙」より)
おおお、なかなかやります。
キダーさんの熱心な教え方が評判を呼び、「キダーさんの学校」の生徒数は増え続けます。やがて、寄宿舎を備えた立派な校舎を建てるまでになりました。このとき建築費を寄付したアメリカの教会の総主事の、フェリスさんの名をとってこの学校はフェリス・セミナリーと名づけられました。
この学校では毎日午前はアメリカから取り寄せた教科書で地理、歴史、生物、数学…すべて英語「で」学び、午後は日本人の先生から和文学、漢籍など習ったそう。プレゼンを重視した教育で、スピーチ、朗唱、意見発表の機会にあふれていました。
そんなフェリスの卒業生第1号は会津出身の若松賤子。短い生涯でしたが
「小公子」をはじめ 膨大な翻訳を残しています。賤子が戊辰戦争で一家離散したのち横浜の生糸商の養女になる経緯は諸説ありますが…8歳から18歳まで、3年のブランクを挟んで在学した賤子は、結婚にあたって夫となる巌本善治にこんな英詩を贈って(つきつけて?!)います。(後ろに日本語訳あり)「結婚は男性が女性を自分の持ち物のように得ると思ったら大間違い!私をモノみたいに得た、と言わないでよ!」と言い切っています。また、「あなたが成長をとめたら、私は離れますから」と「永久就職」とは無縁の境地です。
(後ろに日本語訳あり)
1
We are married, they say, and you think you have won me,
Well, thake this white veil and look on me;
Here’s matter to vex you and matter to grieve you,
Here’s doubt to distrust you and faith to believe you.
I am all, as you see, common earth and common dew,
Be weary to would me to roses, not rue!
Ah! shake out the filmy thing, fold after fold,
And see if you have me to keep and to hold,
Look close on my heart, see the worst of its shining.
It is not yours to-day for the yesterday’s winning,
The past is not mine. I am too proud to borrow.
You must grow to new heights if I love you tomorrow.
2
We’re married! O, pray tat our love do not fail!
I have wings flattened down, and hid under my veil,
They are subtle as light, you can undo them,
And swift in their flight, you can never pursue them.
And spite of all clasping, and spite of all bands,
I can slip like a shadow, a dream. from your hands.
3
Nay, call me not curel and fear not to take me.
I am yours for my life-time to be what you make me.
To wear my white veil for a sign or a cover,
As you shall be proven my lord, or my lover;
A cover for peace that is dead, or a token
Of bliss that can never be written or spoken.
(「女学雑誌」明治22年7月)
いやあ、恐れ入り谷の鬼子母神。これは巌本善治自身も訳せなかったようで、乗杉タツさんが随分後になって訳しています。
1
我ら結婚せりとひとは云う
また君はわれを得たりと思う
然らば、この白きベールをとりて
とくとわれを見給え
見給え、きみを悩ます問題を
またきみを欺かす事柄を
見給え、君を怪しむ疑い心を
またきみを信ずる信頼を
見たもう如く、われはただ、ありふれし土
ありふれし露なるのみ
われを薔薇に造型せんとて
疲れて悔い給うなよ
ああ、このうすものを
くまなくうちふるいて
われとそいとぐべきや 見給え
わが心をとくと見給え
その輝きの最も悪しきところを見給え
昨日君が得られしものは
今日はきみのものならず
過去はわれのものならず
割れは誇り高くして 借り物を身につけず
君に新たに高くなり給いてよ
若しわれ、明日きみを愛さんがためには
2
われはは結婚せり、おお 願わくは
われらの愛の冷めぬことを
われにたためる翼あり
ベールの下にかくされて
光のごとくさとくして
きみにひろげる力あり
その飛ぶ時は速くして
君は追い行くことを得ず
またいかに捕えんとしても
しらなんとしても 影の如く 夢の如く
きみの手より抜け出づる力をわれは持つ
3
いなとよ われを酷と言い給うな
われを取るを恐れた給うな
生ある限り われはきみのものなり
きみの思うがままの者ならん
結婚のしるしとして 覆いとして
わが白きベールをまとわん
きみはわが主
愛しき日となることをあかしせんがため
そは消え去りし平和を覆うもの
また筆舌に表せぬ恵みのしるしなり
これまた日本語も大変なもので…
賤子が自分の心を表現しようとすると、どうしても英語が出てきたようです。「小公子」は、日本語でも心を表現しようと模索した末に生まれた名訳だったのですね。
なんだか今日は長くなってしまいました。次回は「経済」「野球」などおなじみの言葉の誕生を取り上げてみましょうか。
こちらも名訳「クワイ河収容所」英日読書会始めます