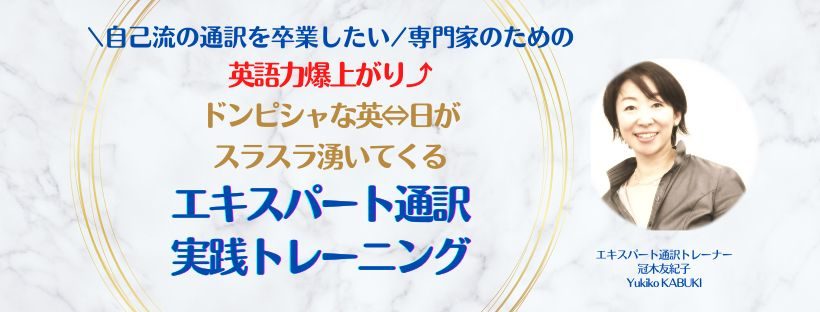【英詩講座レポート⑩】王様も悩ましい
通訳藝術道場の冠木友紀子です。
まったくブログが追い付いていませんが、英詩講座第10回のレポートです。この回はまたまた大物「詩篇23篇」です。
あの、「主はわが羊飼い」で始まる、ダビデ王の有名な詩篇。
私も、これまで礼拝や聖書の授業でなら何度となく触れる機会がありました。
中1のとき、校長先生が担当なさった聖書の授業で出た宿題を忘れもしません。詩篇を水彩で描くことでした。私ふくめ期限の授業で提出できなかった者たちは、教室でその理由を問われ、翌日校長室に持参することを約束しました。次の日、おそるおそる校長室を訪れ、絵を広げると…先生は笑顔で眺め、あれこれとお訊ねになり、それはそれは楽しいひとときでした。「提出期限は約束のひとつだから、次からは守るように。」と笑顔で念押しされ、送り出されたのを覚えています。(さもないと、宿題が遅れるのはラッキー、しめしめと思いかねない楽しさでした。)
ところが、この英語訳を詩としてとらえるのは初めてです。
詩の訳なんて意味がない?
たしかに音をそのまま生かすことはできません。でも、意味や情景を伝えることはできます。言語に新しい刺激を与えたりすることもあるんです。
今回はみなさんに欽定訳の詩篇23篇をよーく観察してもらいました。
| A Psalm of David The Lord is my Shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures; He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul; He leadeth me in the paths of righteousness for His name’ sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: For thou art with me; Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies; Thou annointeset my head with oil; My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the House of the Lord forever (King James Version) | ダビデのうた ヱホバは我が牧者なり われ乏しきことあらじ ヱホバは我をみどりの野にふさせ いこひの水濱にともなひたまふ ヱホバはわが霊魂をいかし 名のゆゑをもて 我をただしき路にみちびき給ふ たとひわれ死のかげの谷を あゆむとも 禍害をおそれじ なんぢ我とともに在せばなり なんぢの笞なんぢの杖われを慰む なんぢわが仇のまへに 我がために筵をまうけ わが首にあぶらをそそぎたまふ わが酒杯はあふるるなり わが世にあらん限りはかならず 恩惠と憐憫とわれにそひきたらん 我はとこしへにヱホバの宮にすまん (文語訳) |
「ん?韻は踏んでませんね。」
そのとおり。
「これまでのもともと英語の英詩と何かちがう…」
何か違う、のは何かが多すぎるのですか?それとも少なすぎるのですか?あるいは思いがけないものが入っているのでしょうか?
「あ…少ないんです。というか、ほとんどないんです。」
なにが?
「形容詞や副詞が。」
そう、まさにそれがヘブライ詩の特徴です。
韻は踏みません。
新築マンションのチラシのように修飾語で飾り立てることもしません。
「3音節以上の語もありません!」
本当に!さっぱりしたヘブライ詩の特徴と「誰でも読める聖書を」と願ったティンダルの願いを合わせて受け継いでいるようですね。
また、詩篇23篇ではわかりにくいかもしれませんが、パラレリズムといって一つのことをいろいろ言い換えて繰り返すのもヘブライ詩の特徴です。
ここでは、神の恵みに守られたありようを「羊」になったつもりで描いたり、「敵の前に宴を」「わが頭に油を注ぎ」と人にもどって描いたりしています、
さて、つらい思いをしてこそ惹かれるのが「我れ死の影の谷を歩むとも、災いを恐れじ」の一節。
災いが「ない」のではなく「そりゃあるだろうけど、びびらない」のがいいじゃないですか。このごろはゼロ放射能とかゼロコロナじゃないと、とうい人までいるそうですから。
これはあどけない幼子には???な気分でしょう。自分は世界から切り離されている、という寂しさに気づくとされる3年生以上には覚えがあるでしょうか。
でも、王様ダビデもそんな思いを…?

この一節でダビデが何を想ったのかは推測の域を出ませんが、ダビデはなかなか人間臭いエピソードが豊かです。絵画や彫刻のモチーフとしても魅力的なのは聖人君子ではないからかもしれません。
ダビデはイスラエル王国第2代の王です。在位期間は諸説ありますが、紀元前1000年を挟んでの数十年とされています。
王といってもダビデ自身が王子だったわけではありません。もとは初代王、サウルの宮廷にハープの名人として召し抱えられます。その賢さからサウルの息子と親しくなり、サウルの娘と結婚します。サウルを悩ませたペリシテ人との戦いでは、巨人ゴリアテの眉間に石を命中させた逸話が知られます(あのダビデ像です!!)。
ただ、ここまで魅力的だと嫉妬がつきものです。
なんとサウル王にうとまれ、命の危険にさらされます。サウル亡き後王位につき、イスラエルは繁栄したかに見えますが、すでに在位中から下り坂の兆しがちらほらと。なんとダビデ王自身が部下ウリヤの奥さんバテシバが水浴びをしている姿にムラムラし…ウリヤは絶望のあまり自ら命を絶ちます。預言者ナタンに厳しくとがめられ。ダビデは反省します。やがてバテシバとの間に生まれたソロモンが王位につきます。
いやはや…。
おまけに詩篇150篇をすべて自分で作ったとしたら…。
アウトプットすごすぎます。
ええ、詩篇にはダビデ含め複数の作者がいるとされています。なぜなら、神をヤハウェ、エロヒムと明らかに違う呼び方をしたり、ダビデの死後起きた出来事が含まれたりしているためです。
さて、第11回のヨハネの福音書冒頭「はじめにことばがあった」ももう済んでいまして、次回、最終回とシェイクスピアの「真夏の世の夢」「あらし」からセリフを詩として味わいます。
【シュタイナー学校の先生のための英詩講座 4年生シリーズ あと2回!】